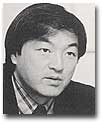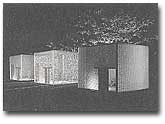インターデザインフォーラム TOKYO 2025 VOL36
インターデザインフォーラム TOKYO 2025 VOL35
インターデザインフォーラム TOKYO 2025 VOL34
インターデザインフォーラム TOKYO 2024 VOL32
インターデザインフォーラム TOKYO 2024 VOL31
インターデザインフォーラム TOKYO 2024 VOL30
インターデザインフォーラム TOKYO 2024 VOL29
インターデザインフォーラム TOKYO 2023 VOL27
インターデザインフォーラム TOKYO 2023 VOL26
インターデザインフォーラム TOKYO 2023 VOL25
インターデザインフォーラム TOKYO 2022 VOL22
インターデザインフォーラム TOKYO 2022 VOL21
インターデザインフォーラム TOKYO 2022 VOL20
インターデザインフォーラム TOKYO 2021 VOL18
インターデザインフォーラム TOKYO 2021 VOL17
インターデザインフォーラム TOKYO 2020 VOL15
インターデザインフォーラム TOKYO 2020 VOL14
インターデザインフォーラム TOKYO 2020 VOL13
インターデザインフォーラム TOKYO 2019 VOL12
JIDF学生文化デザイン賞2019
インターデザインフォーラム TOKYO 2019 VOL11
インターデザインフォーラム TOKYO 2019 VOL10
インターデザインフォーラム TOKYO 2018 VOL9
JIDF学生文化デザイン賞2018
日本文化デザインフォーラム 2012 アートプロジェクト with 北本ビタミン
BS12TwellVでの番組『発想力学~トップクリエイターのアタマの中~』
里山のつどい・日本文化デザインフォーラム「自然学」プロジェクトin秦野
日本文化デザイン会議 2010 アートプロジェクト with 北本ビタミン
| [授賞委員長] | 鈴木博之 |
| [授賞委員] | 秋元康 |
| 川崎徹 | |
| 今野由梨 | |
| 坂村健 | |
| 中村宗哲 | |
| 野村万之丞 | |
| 松岡正剛 |
|